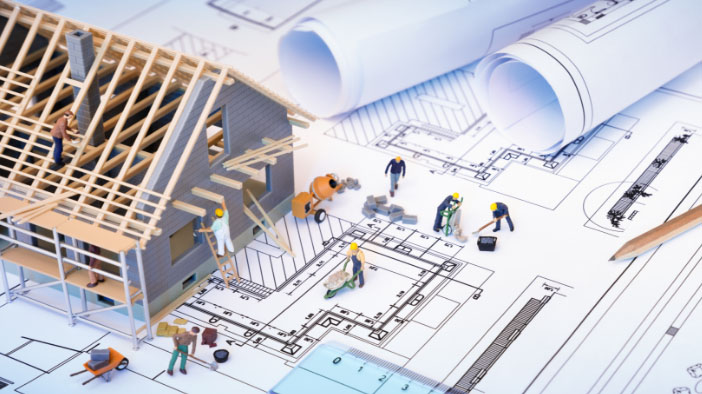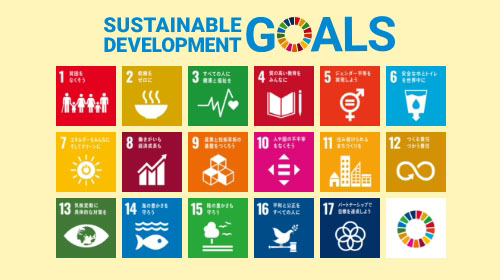注文住宅を建てるなら知っておきたい、「坪単価」とは?
注文住宅を検討し始めると、必ず目にするのが「坪単価」という言葉でしょう。坪単価は注文住宅を建てる費用の目安を知るために重要な情報ですが、坪単価だけでの単純比較はおすすめできません。後悔しない家づくりのためには、まず坪単価の正しい意味を理解し、総額費用を把握する必要があります。坪単価の基本を詳しく解説します。
坪単価とは何か
注文住宅における坪単価とは、建物本体の建築費用を、建物の延床面積(坪数)で割った、1坪(約3.3㎡)あたりにかかる建築費用の目安を示す指標です。家づくりの初期段階で、メーカーの価格帯を大まかに比較検討するために使用されます。
しかし、ハウスメーカーによっては「工事面積」のような異なる基準を使う場合があります。そのため、比較の際は計算方法の基準が重要な点を理解しておきましょう。
坪単価の計算方法
坪単価は、以下の計算式で求められます。
たとえば、建物本体価格が2,000万円、延床面積が40坪の家の場合、坪単価は50万円となります。 このように坪単価を計算すると、異なる広さの住宅の建築費用を比較検討する際の目安として役立ち、初期の資金計画を立てやすくなるのです。
坪単価に含まれる費用・含まれない費用
注文住宅の坪単価は建物本体の1坪あたりの建築費用を示す指標ですが、含まれる費用と含まれない費用が存在します。それぞれの項目を紹介します。
坪単価に含まれる費用
坪単価には、建物本体を建築するための本体工事費が含まれます。
<坪単価に含まれる費用(本体工事費)の例>
| 項目 |
概要 |
| 基礎工事 |
建物の土台部分を作るための工事費用(地盤の状態に応じた基礎の設置を含む) |
| 躯体工事 |
柱や梁、屋根など、建物の主要な構造部分を構築する工事 |
| 外装工事 |
外壁や屋根など、建物の外部を仕上げるための工事 |
| 内装工事 |
フローリング、壁紙、天井材など、建物内部の仕上げにかかる工事 |
| 住宅設備工事 |
キッチン、浴室、トイレなどの標準仕様の設備設置費用 |
| 給排水・電気設備工事 |
建物内部の配管や配線工事 |
坪単価に含まれない費用
坪単価には、建物本体以外にかかる費用(付帯工事費や諸費用)は含まれません。
<坪単価に含まれない費用の例>
| 項目 |
概要 |
| 付帯工事費 |
地盤改良工事、外構工事(駐車場・フェンス等)、インフラ引き込み工事など |
| 諸費用 |
登記費用、住宅ローン手数料、火災保険料、各種税金(印紙税・不動産取得税等)など |
| オプション費用 |
標準仕様外の設備、エアコン・照明器具、カーテン・ブラインドなど |
| その他 |
地鎮祭・上棟式費用、家具・家電の購入費など |
なぜ坪単価が重要なのか
坪単価は、家づくり全体の予算計画を立てるうえでの目安として役立ちます。
坪単価は建物を建てる費用を把握するための指標であり、土地代や諸費用は含まれません。そのため、坪単価を用いて建物建築の大まかな予算を立て、住宅取得の予算の総額から土地分と切り分け、資金配分を適切に把握できます。
また、坪単価はハウスメーカーの価格帯を比較する際の目安としても活用できます。ただし、最終的な判断は必ず建物本体価格に加えて、別途必要な付帯工事費や諸費用を含めた総額で比較する必要があります。見積もり時には「坪単価に何が含まれているか(標準仕様)」と「別途必要な費用は何か」を必ず確認し、後悔のない資金計画を立てましょう。
注文住宅の坪単価の相場は?
注文住宅の坪単価は、建物の構造、ハウスメーカーの種類、設備のグレードなどによって変動します。大まかな目安は公的なデータで把握できます。国土交通省のデータを見ていきましょう。
建物の構造別坪単価の相場
注文住宅の坪単価は、建物の構造によって大きく異なります。以下は、国土交通省の建築着工統計調査(2025年8月調査分)から、新築注文住宅の構造別の坪単価を比較した表です。
<建物の構造別坪単価の平均額>
| 構造 |
坪単価 |
| 鉄筋コンクリート造 |
145.2万円 |
| 鉄骨造 |
122.1万円 |
| コンクリートブロック造 |
99.0万円 |
| 木造 |
85.8万円 |
坪単価が低めの木造住宅
上記の結果から、木造住宅は他の構造と比較して坪単価が安い傾向にあるとわかります。日本では、低層の住宅の多くが木造住宅です。
エリア別坪単価の相場
坪単価はエリアによっても変動します。以下は同じ国土交通省の建築着工統計調査(2025年8月調査分)から、都道府県別(抜粋)の木造新築注文住宅の坪単価をまとめた表です。
<都道府県別坪単価の平均額>
| 都道府県 |
坪単価 |
| 北海道 |
89.1万円 |
| 岩手県 |
89.1万円 |
| 宮城県 |
85.8万円 |
| 福島県 |
85.8万円 |
| 茨城県 |
85.8万円 |
| 栃木県 |
85.8万円 |
| 群馬県 |
85.8万円 |
| 埼玉県 |
79.2万円 |
| 千葉県 |
85.8万円 |
| 東京都 |
95.7万円 |
| 神奈川県 |
89.1万円 |
| 山梨県 |
89.1万円 |
| 長野県 |
102.3万円 |
| 岐阜県 |
85.8万円 |
| 静岡県 |
85.8万円 |
| 愛知県 |
85.8万円 |
| 大阪府 |
75.9万円 |
| 島根県 |
92.4万円 |
| 広島県 |
85.8万円 |
| 山口県 |
89.1万円 |
| 愛媛県 |
82.5万円 |
| 福岡県 |
85.8万円 |
FPからの補足
坪単価に土地代は含まれませんが、人件費や資材の輸送費、寒冷地仕様などの違いにより、建築費(坪単価)にも地域差は発生します。統計上で複数の県が同額になっているのは、集計上の平均値が反映されているためであり、個別の費用とは異なる点を理解しておきましょう。

注文住宅を坪単価で比較する際のポイント
坪単価を正しく比較するには、計算基準の理解が不可欠です。ハウスメーカー間で特に違いが出やすい延床面積と工事面積の基準の違いや、標準仕様に含まれる設備・性能の範囲、そして表面的な安さだけにとらわれないための注意点を解説しましょう。
延床面積と工事面積の違い
坪単価を比較する際に注意すべきなのが、計算の土台となる面積の基準です。坪単価は建物の本体価格を延床面積で割って求めるのですが、延床面積の代わりに工事面積を用いる住宅メーカーもあります。
延床面積とは
延床面積とは、建物の各階の床面積をすべて合計した面積です。延床面積は建築基準法にもとづいて算出され、固定資産税の計算などにも使われる公的な面積です。延床面積には、バルコニーやロフト、吹き抜けなどは含まれません。
工事面積とは
一方、工事面積は、建物全体の工事が行われるすべての部分の面積を指します。延床面積と異なり、住宅会社によって算出基準や含まれる範囲が異なります。延床面積に含まれない、バルコニーや玄関ポーチも工事面積に含まれるのが一般的です。工事面積は延床面積より広くなるため、工事面積で坪単価を計算するほうが延床面積を用いるより安く見えます。
標準仕様に含まれる内容の違い
坪単価を比較するうえで、計算の基準面積と並んで重要なのが、価格に「何が含まれているか」です。坪単価はハウスメーカー各社が想定している標準仕様(キッチン、浴室、トイレ、外壁、断熱材などの設備や建材)の種類、メーカー、そしてグレードにもとづいて算出されます。
たとえば、A社とB社が同じ坪単価80万円でも、A社はハイグレードなシステムキッチンや高性能な断熱材を標準仕様としているのに対し、B社は基本的な設備のみで、希望のグレードに上げるには高額なオプション費用が必要になるケースは少なくありません。
表面的な坪単価の数字に惑わされず、標準仕様の充実度や性能まで比較したほうが、結果的に総額費用を抑え、満足度の高い家づくりにつながります。
安さだけにこだわるリスク
坪単価の安さだけに注目してしまうと、表面上のコストダウンに惑わされ、後から思わぬ追加費用や性能低下に直面するリスクが高まります。低い坪単価を提示する住宅メーカーは、最低限の建物本体価をベースに算出しているケースが少なくないためです。
たとえば、家の断熱性能が低いために坪単価が低い住宅の場合、建てた後の光熱費が高くなり、毎月のランニングコストが家計を圧迫します。また、坪単価に含まれる標準仕様が最低限の場合、希望するキッチンやサッシなどの設備をグレードアップする際に、高額なオプション費用が積み重なり、結局総額で高くなる可能性もあるでしょう。
家づくりでは初期費用(坪単価)だけでなく、建ててからの総コストでの判断も重要です。
注文住宅の坪単価を抑えるコツ
坪単価を抑えるために安さにこだわりすぎると、後から追加の費用がかかったり、住まいの性能が低下したりするリスクがあります。賢く坪単価を抑えるには、削ってはいけない性能と効率的に削れる部分を分ける必要があります。設計や間取り、そしてハウスメーカー選びの視点から、性能を犠牲にせずに坪単価を抑えるためのコツを解説します。
建物の形状をシンプルにする
坪単価を効率的に抑えるには、建物の形はシンプルなほうが望ましいでしょう。同じ延床面積(坪数)の家を建てる場合でも、建物の形状の違いによって建築コストが変動し、坪単価に反映されるためです。
具体的には凹凸が少なく、総2階建てのシンプルな箱型の建物が最もコストを抑えやすくなります。シンプルな形状の建物は外壁や屋根の外周が短くなり、外壁材や屋根材、構造材といった使用する材料の量が少なくて済みます。
一方、コの字型やL字型といった複雑な形状の家は、構造が複雑になるだけでなく、工事の手間も増え、坪単価が割高になる傾向です。コストを抑えたい場合は、理想の間取りは維持しつつ、建物の外観はできるだけ四角く整える工夫が有効です。
部屋数・間仕切りを最小限にする
注文住宅で複雑な間取りや部屋数が多い設計は、坪単価が上がる大きな要因です。壁やドアといった間仕切りの数が増えるほど、材料費や工事の手間が増加するためです。
コストを抑えるためには必要最小限の部屋数に絞り込み、間取りをシンプルにするのが有効でしょう。たとえば、子ども部屋を将来的に間仕切る想定で、初期段階では大きなワンフロアとして計画するなどが挙げられます。また、キッチンや浴室などの水回りを近い位置にまとめたり、上下階で重ねて配置したりすると、配管工事費を削減できます。建物の形状だけでなく、内部の間取りの工夫も、坪単価を賢く抑えるポイントです。
標準仕様の充実した住宅メーカーを選ぶ
坪単価を抑える最大のコツは、グレードの高い設備や家の基本性能が最初から標準仕様に含まれている住宅メーカーを選ぶ点です。
坪単価の安い住宅メーカーは、標準仕様の内容を最低限に抑えているケースが少なくありません。希望する仕様の多くがオプションとなっていて、結果的に総額費用が膨らんでしまいます。安さに惹かれて契約したにもかかわらず、予算オーバーになりかねません。
初期の坪単価が他社と同等か、わずかに高く見えても、断熱材、窓サッシ、水回り設備といった、生活の快適性や光熱費に直結する重要な要素が標準で高グレードであれば、オプション費用や建ててからのランニングコストを大幅に削減できます。
坪単価を比較する場合、標準仕様の内容や特徴のチェックも忘れないようにしましょう。
性能には妥協しない
坪単価を抑える工夫は大切ですが、家の性能だけは妥協しない姿勢が、長期的なコストダウンと快適性の確保につながります。特に、断熱性・気密性といった基本性能を低くして建築費を下げると、後の生活で大きな負担となって跳ね返ってきます。
断熱性能が低い家は冷暖房効率が悪く、光熱費が高くなるため、低い坪単価で浮いた初期費用を高額な電気代で失いかねません。また、耐震性や耐久性といった構造の性能を落とすと、将来の修繕・メンテナンス費用が高額になるリスクがあります。
初期費用とランニングコストのバランスを取り、長い目で見て高品質の家を建てるようにしましょう。
坪単価の
「カラクリ」を知り
賢いハウスメーカーを
選びませんか?
坪単価はハウスメーカーによって計算基準(延床面積か工事面積か)が異なり、単純比較は危険です。
「坪単価が安く見えても、
付帯工事費やオプション費用で
結局高額になるのでは?」
「安い家を選んで断熱性能が低く、
入居後の光熱費で後悔したくない」
注文住宅を検討する多くの方が、坪単価という「入口」の数字と「最終的な総額」のギャップに不安を抱えています。
アエラホームは、お客様の不安を解消し、「総額」と「住宅性能」でご満足いただく家づくりを大切にしています。

アエラホームが「標準仕様」にこだわる理由
アエラホームは、目先の坪単価の安さだけを追求しません。
コラムの「坪単価を抑えるコツ」で解説したように、「標準仕様の充実」 こそが、お客様の最終的な満足とコスト削減につながると知っているからです。
高性能な断熱材や設備が「標準」の安心
アエラホームの住まいは、生活の快適性や光熱費に直結する「断熱性・気密性」 といった基本性能を妥協しません。
高性能な断熱材や窓サッシ、充実した設備が標準仕様。
そのため、オプション費用で予算が膨らむ不安を軽減し、「価格と価値のバランス」 に優れた住まいをご提供します。

「坪単価」ではなく「総額」と「将来の光熱費」でご提案します
家づくりで本当に重要なのは、坪単価ではなく「総額でいくらかかるか」、そして「住んでからのランニングコスト」です。
アエラホームの「家づくり・資金計画相談会」では、建物本体価格はもちろん、坪単価に含まれない付帯工事費や諸費用まで含めた「総額」での資金計画を丁寧にご説明します。さらに、高い省エネ性能によって、入居後の光熱費をどれだけ抑えられるかまでシミュレーション。
お客様の不安を「見える化」し、解消するお手伝いをいたします。
まずは展示場で「価格以上の価値」を体感してください
「高性能な標準仕様」がどのようなものか、ぜひお近くの展示場でご体感ください。
デザインだけでなく、なぜアエラホームが性能にこだわるのか、その理由と価値がきっとお分かりいただけます。
坪単価は入口。総額と長期的コストで判断を
坪単価は、家づくりの予算を考えるうえで、ハウスメーカーや工務店を比較する際の重要な目安となるでしょう。ただし、坪単価の計算に含まれる項目は住宅メーカーによって異なる場合もあるため、計算基準(延床面積か工事面積か)と標準仕様の内容を確認してから比較する必要があります。
FPの視点から強調したいのは、「目先の坪単価の安さ」だけに注目するリスクです。 坪単価が安くても、断熱性や耐震性といった基本性能が低ければ、入居後の光熱費(ランニングコスト)が家計を圧迫し、将来の修繕費(ライフサイクルコスト)も高額になりがちです。
初期費用が安くても、長期的には損をしてしまう可能性が高いのです。
家づくりで後悔しないためには、坪単価はあくまで目安の一つと捉え、性能・品質とのバランス、そして「総額でいくらかかるのか」を誠実に説明してくれる、信頼できる会社を選びましょう。