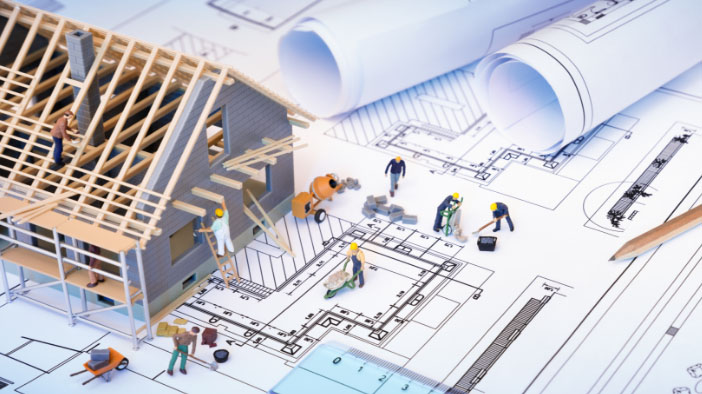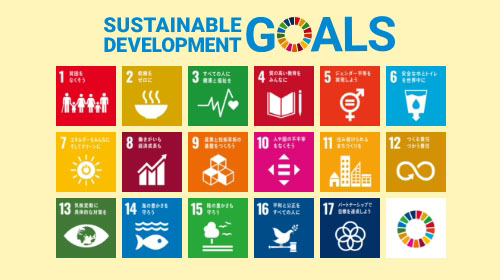土地あり注文住宅の費用相場と自己資金準備のポイント
土地を所有している方が注文住宅を建てる場合、土地代は不要です。しかし、建築費は地域や住宅の仕様によって大きく変動します。ここでは、土地あり注文住宅の建築費相場と、自己資金準備のポイントについて解説します。
全国の平均建築費用と地域差
注文住宅の建築費の平均は、エリアによって異なります。
住宅金融支援機構のデータから、土地ありの注文住宅の建築費の全国平均と、主な都道府県別の平均額を紹介しましょう。
<土地ありの注文住宅の建築費の平均額>
| 全国 |
3,861万円 |
| 北海道 |
4,580万円 |
| 宮城県 |
3,448万円 |
| 東京都 |
4,625万円 |
| 愛知県 |
4,046万円 |
| 新潟県 |
3,492万円 |
| 大阪府 |
4,406万円 |
| 広島県 |
3,959万円 |
| 愛媛県 |
3,425万円 |
| 福岡県 |
3,847万円 |
| 沖縄県 |
3,902万円 |
建築費にも地域差がある
住宅金融支援機構のデータによると、土地あり注文住宅の建築費全国平均は約3,861万円です。しかし、地域によって建築費には大きな差があるはご存じでしょうか。
たとえば、東京都は約4,625万円、愛媛県は約3,425万円と、1,000万円以上の差が見られるのです。
理由として、地域ごとの人件費や建材輸送コストや、気候に応じた建築仕様の違いなどが影響していると考えられます。
自己資金と住宅ローンの割合
建築費全体に対する自己資金と住宅ローンの割合を、先ほどの住宅金融支援機構のデータの全国平均の資金の内訳から見てみましょう。
<土地ありの注文住宅の建築費の資金の内訳(全国平均)>
・建築費:3,861.3万円
・自己資金:697.9万円(18%)
・住宅ローンなどの借り入れ:3,163.4万円(82%)
|
一般的に、頭金は建築費の20%程度、諸費用は建築費の5〜10%程度が目安とされています。たとえば、建築費が3,000万円の場合、頭金600万円、諸費用150万円〜300万円、合計750万円〜900万円程度の自己資金が必要になります。
<建築費3,000万円の場合に準備すべき自己資金>
・頭金:600万円(20%)
・諸費用:150万円~300万円(5~10%)
・合計:750万円~900万円
|
自己資金準備のポイント
自己資金を多く用意できるほど、住宅ローンの返済負担を軽減できます。自己資金をしっかり準備し、無理のない資金計画を立てることが大切です。
自己資金準備のポイントを確認しておきましょう。
| 早めに貯蓄を始める |
目標額を決め、毎月コツコツと貯蓄しましょう。 |
| 財形住宅貯蓄制度を活用する |
利子非課税制度を利用できます。 |
| 両親や親族からの援助を検討する |
贈与税の非課税枠を活用できる場合があります。 |

土地ありで家を建てる場合の費用の内訳
土地を所有している状態で注文住宅を建てる場合、費用は主に「本体工事費」「別途工事費」「諸費用」の3つに分けられます。それぞれの費用項目と支払いタイミングを把握し、余裕のある資金計画を立てましょう。
<土地ありで家を建てるときの費用の内訳>
・本体工事費
・別途工事費
・諸費用
|
本体工事費
本体工事費は、住宅の基礎工事から完成までにかかる主要な費用です。建築費全体の70~80%を占め、工事の進捗に応じて分割で支払われます。住宅ローンのつなぎ融資を利用するケースも。
まずは、主な工事内容について確認しておきましょう。
<本体工事費に含まれる工事>
・仮設工事(足場、工事用電器、現場用トイレの設置など)
・基礎工事(基礎部分の施工など)
・躯体工事(柱、梁、床、屋根など)
・外装工事(外壁、屋根材など)
・内装工事(床材、壁紙、建具など)
・設備工事(電気、給排水、空調など)
|
本体工事費の支払いのタイミング
本体工事費は、一般的に工事進捗の過程のなかで、いくつかのタイミングで支払いが発生します。
<本体工事の支払いのタイミング>
| 支払時期 |
支払い金額(工事費に対する割合) |
| 契約時(手付金) |
10% |
| 着工時 |
30% |
| 上棟時 |
30% |
| 完成引き渡し時 |
30% |
別途工事費
別途工事費は、建物本体以外にかかる工事費用で、建築費全体の15~20%を占めます。見積書では本体工事費と区別して記載されるのが一般的です。ただし、別途工事費の扱いは建築会社によって異なるため、事前に確認が必要になるでしょう。
別途工事費は住宅ローンに組み入れることができ、つなぎ融資も利用できます。
<別途工事費に含まれる工事>
・外構工事(駐車場、門扉、フェンス)
・インフラ工事(上下水道、ガス、電気の引き込み)
・地盤改良工事
・解体工事
|
別途工事費の支払い方法と支払いタイミング
別途工事費の支払い方法には、建築会社による一括清算と、施主による個別清算があります。それぞれの支払いタイミングも確認しておきましょう。
<別途工事費の支払い方法ごとの支払いタイミング>
|
建築会社による一括清算 |
施主による個別清算 |
| 内容 |
建築会社が施工業者へ立て替え払い |
施主が各施工業者へ直接支払い |
| 支払うタイミング |
契約時・着工時・上棟時・完成時(本体工事費と同様) |
工事完了ごとに都度支払い |
諸費用
諸費用は建築費以外にかかる費用で、建築費の5~10%が目安です。
諸費用はその都度、原則として現金での支払いが必要となります。主な費用と支払いタイミングも知っておきましょう。
<諸費用の種類と発生するタイミング>
| 契約時 |
・工事請負契約書の印紙代
・住宅ローン手数料 |
| 完成時 |
・建物登記費用
・火災保険料
・不動産取得税 |
| 入居時 |
・引越し費用
・家具・家電購入費 |
アエラホーム主催【初心者向け】初めての住宅ローン相談会とは?
「家を買いたいけど、住宅ローンを勉強するのは大変そう…」
そんな不安をお持ちのあなたへ。
アエラホームが、住宅ローン初心者の方に向けて、わかりやすく丁寧な相談会を開催します!

アエラホーム主催の相談会に参加するメリット
・経験豊富な専門家が個別にアドバイス
住宅ローンのプロが、あなたの状況に合わせて最適なライフプランをご提案します。金利の種類、返済方法、借入額など、疑問を解消し、安心して家づくりの一歩を踏み出してみませんか?
・無理のない返済計画を立てられる
将来のライフプランも考慮しながら、無理のない返済計画をシミュレーション。家計の負担を軽減し、ゆとりある生活を実現するためのお手伝いをします。
・住宅ローンに関する不安を解消できる
「頭金はいくら必要?」「どんな手続きが必要?」など、住宅ローンに関する疑問や不安を解消できます。
・アエラホームの家づくりについて詳しく知れる
高気密・高断熱で快適な住まいを提供するアエラホームの家づくりについて、詳しく知ることができます。理想の家のイメージを膨らませながら、資金計画も同時に進められます。
アエラホームのこだわりの家とは…
・高気密・高断熱で夏は涼しく、冬は暖かい快適な住まい
・耐震性に優れ、地震から家族を守る安心の構造
・自由設計で、理想のライフスタイルを実現
相談会は予約制です。
お申し込みは、アエラホームのホームページまたは下記バナーより、お気軽に申し込みできます。
「初めての住宅ローン相談会」で、夢のマイホーム実現に一歩近づきましょう!
アエラホームで、安心・快適な家づくりを始めませんか?
土地あり注文住宅の予算設定から引き渡しまで8ステップ
土地を所有している状態で注文住宅を建てる場合、予算設定から引き渡しまで、どのような手順で進めれば良いのでしょうか?土地あり注文住宅は、土地購入費が不要な分、建築費に予算を集中できます。
しかし、予算設定や施工会社選びは慎重に行う必要があるでしょう。この記事を参考に、スムーズな家づくりを進めてください。
ここでは、8つのステップに分けて解説します。
<土地ありで家を建てる8つのステップ>
1. 予算設定
2. 施工会社選定
3. 家のプランを決める
4. 住宅ローン事前審査
5. 工事請負契約
6. 住宅ローン本審査
7. 着工
8. 引き渡し
|
【1】予算設定
土地ありで注文住宅を建てる場合、土地購入費は不要ですが、予算設定は慎重に行いましょう。自己資金は建築費の25%程度を確保し、予備費も見込んでください。
具体的には、用意できる自己資金から逆算して建築費を決定します。たとえば、自己資金が600万円であれば、建築費は2,400万円程度が適切な予算と考えられます。
【2】施工会社選定
注文住宅における施工会社選びは、家づくりの成否を左右する重要な要素です。以下の点を考慮して選びましょう。
<注文住宅を建てる場合の施工会社選定のポイント>
| 施工実績の確認 |
過去の施工事例から、デザインや品質が自身の希望に合っているか確認しましょう。 |
| 性能へのこだわり |
省エネ性能に優れた住宅を提供しているか確認しましょう。 |
| 見積もりの透明性 |
見積もり費用項目が明確であるか確認しましょう。 |
| 担当者の信頼性 |
レスポンスが良く、対応力に優れた担当者がいるか確認しましょう。 |
| アフターサービスの充実 |
施工後の保証やサポート体制が整っているか確認しましょう。 |
【3】家のプラン決定
施工会社と相談しながら、家族構成やライフスタイルに合った住宅プランを決定します。間取りやデザインだけでなく、将来的な家族構成の変化も考慮しましょう。
【4】住宅ローン事前審査
住宅ローンを利用する場合は、事前に金融機関で事前審査を受けましょう。借入可能額や金利タイプなどを把握できます。
【5】工事請負契約
住宅プランと資金計画が確定したら、施工会社と工事請負契約を締結します。契約内容をしっかりと確認しましょう。
【6】住宅ローン本審査
工事請負契約締結後、金融機関で住宅ローン本審査を受けます。審査に通れば、融資が実行されます。
【7】着工
住宅ローン融資が実行されたら、いよいよ着工です。工事期間中は、現場の進捗状況を定期的に確認しましょう。
【8】引き渡し
建物が完成したら、施工会社による最終確認を行い、引き渡しとなります。引き渡し後も、定期的なメンテナンスを行いましょう。
知っておきたい!注文住宅の費用を抑えるポイント
せっかくのマイホーム、こだわりを詰め込みたい気持ちは誰しもが抱くもの…。
しかし、注文住宅では予算との兼ね合いも重要になってきます。そこで、無理なく費用を抑えつつ、質の高い家づくりを実現するためのポイントを3つご紹介します。
<注文住宅の家づくりの費用を抑えるポイント>
・希望条件に優先順位を付ける
・シンプルなデザインと間取りを選ぶ
・標準仕様が充実した施工会社を選ぶ
|
希望条件に優先順位を付ける
家づくりの費用を抑えるためには、希望条件に優先順位をつける必要があるでしょう。
注文住宅ですべての要望を叶えようとすると、どうしても予算オーバーになりがちです。優先順位を決めることで、本当に重要な部分に予算を集中できます。
たとえば、「断熱性能」「収納力」「デザイン性」のうち、断熱性能を最優先にすると決めれば、収納は既製品で対応したり、外観は必要最小限のデザインに抑えたりといった具体的な判断ができます。
希望条件の優先順位を正しく設定すれば、費用対効果だけでなく満足度も高い家づくりを実現できるはずです。
シンプルなデザインと間取りを選ぶ
シンプルなデザインと間取りの採用は、家づくりの費用を大幅に削減する有効な手段です。複雑な形状や余計な仕切りは、材料費や施工工数を増やし、全体のコストを押し上げてしまいます。
たとえば、総二階建ての直線的な外観に、仕切りの少ないオープンなレイアウトを採用し、延べ床面積を必要最低限に抑える方法が考えられるでしょう。また、窓やドアの数と配置を見直したり、キッチン、バスルーム、トイレなどの水回りを隣接配置したりすることで、配管工事の手間や資材費を節約できます。工夫により、効率的で経済的なマイホームに近づけることができるのです。
標準仕様が充実した施工会社を選ぶ
家づくりの費用を抑えるには、標準仕様が充実した施工会社を選ぶことが近道です。標準仕様が充実していれば、後からオプションを追加する必要がなく、余分な費用が発生しにくくなります。
具体的には、エコキュートのような省エネ設備が初期仕様で確保できれば、建築費を抑えながら快適な住まいが手に入るはず。標準仕様で高性能な設備を採用している施工会社を選ぶと、予算内で希望する家づくりができるでしょう。

相続・贈与された土地に家を建てる際の注意点
土地ありで家を建てる人の中には、親や祖父母から土地をもらったケースも多いでしょう。住宅用の土地の相続や贈与の注意点を解説します。
土地を相続したら相続登記が必要
相続した土地に家を建てる場合、まず相続登記が必要です。2024年4月1日以降、相続により取得した不動産は、相続開始または遺産分割成立の日から3年以内に必ず相続登記をしなければならなくなりました。
相続登記は、住宅ローンを組む際にも不可欠です。金融機関はローンの担保として土地に抵当権を設定しますが、相続登記をしていない土地には抵当権を設定できません。そのため、相続登記がすんでいないと住宅ローンの契約ができないのです。
相続が発生したら必要な書類を早急に揃え、登記手続きを速やかに進めましょう。
相続税がかかる場合
土地を相続した場合、相続財産の合計額が基礎控除を超えると相続税がかかります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。たとえば、相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。
相続税がかかるケースでも相続した土地が被相続人(亡くなった人)の自宅の敷地だった場合、「小規模宅地等の特例」が適用できます。この特例により、330㎡までの土地について評価額を80%減額できます。たとえば、評価額3,000万円の土地であれば、特例適用後は240万円として計算されるのです。
生前贈与を受けた場合
親や祖父母から土地を生前贈与してもらう場合、贈与税がかかります。贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの制度があり、贈与者(親など)と受贈者(子や孫)の間で使い分けられます。
暦年課税
暦年課税制度では、年間110万円までの贈与であれば非課税となります。暦年課税では複数年に分けた贈与によって、税負担を抑えることができます。ただし、相続開始前7年以内の贈与はなかったものとされ、相続財産に含めて相続税を計算する点に注意が必要です。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は60歳以上の親から18歳以上の子や孫への贈与に適用され、最大2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。2024年1月からは年間110万円の基礎控除も利用できるようになりました。
贈与者が亡くなった場合、その贈与財産は相続財産となり、あらためて相続税が計算されます。このとき、すでに納めた贈与税は相続税から差し引かれます。
一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻れず、小規模宅地等の特例も使えなくなる点に注意が必要です。
家を建てるにあたっての土地の状況確認
相続した土地に家を建てる際には、その土地が住宅を建てるための条件を満たしているかの確認が必要です。確認すべき項目には、主に以下のような法令上の制限事項と敷地状況があります。
<もらった土地に家を建てられるかのチェックポイント>
| 土地の制限事項 |
敷地状況 |
・用途地域による建築制限
・建ぺい率・容積率の上限
・高さ制限や日影規制
・建築基準法上の接道要件(幅4m以上の道路に2m以上接している) |
・土地の形状や高低差
・日当たりや通風の状況
・給排水、電気、ガスなどのライフラインの整備状況
・地盤調査による地耐力の確認 |
地目変更が必要な場合にどうすればいいか
相続や贈与で譲り受けた土地が農地の場合、家を建てる前に「農地転用」の手続きが必要です。農地転用とは、農地を宅地などに変更して利用する制度です。許可が下りるまでには一定の期間がかかるため、早めに準備を進めましょう。農地転用の手続きの一般的な流れは、以下のとおりです。
<農地転用の手続きの流れ>
1. 農業委員会への事前相談
2. 必要書類の準備
3. 農業委員会への申請書提出
4. 農業委員会による審査
5. 許可後、法務局で地目変更登記 |
建築費だけじゃない!ランニングコストも考慮した家づくり
土地ありで家を建てる場合、建築費に注目しがちですが、住み始めてからのランニングコストも重要な要素です。建築費を抑えれば住宅ローンの返済負担軽減に繋がりますが、光熱費などのランニングコストも考慮に入れる必要があります。
省エネ性能の高い住宅は、光熱費を削減できるだけでなく、国や自治体の補助金制度、住宅ローン金利の優遇措置などを受けられる場合があるのです。
たとえば、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)住宅は、断熱性能や省エネ設備を導入することで、年間の一次エネルギー消費量の実質ゼロを目指した住宅です。ZEH住宅には、国や自治体から補助金が交付される制度があります。
また、長期優良住宅も、省エネ性能や耐震性能などに優れた住宅として認定されると、住宅ローン金利の優遇措置を受けられます。
建築会社を選ぶ際には、省エネ性能について詳しく説明を受け、比較して検討する時間が大切です。将来的なランニングコストも考慮した上で、最適な住宅を選びましょう。