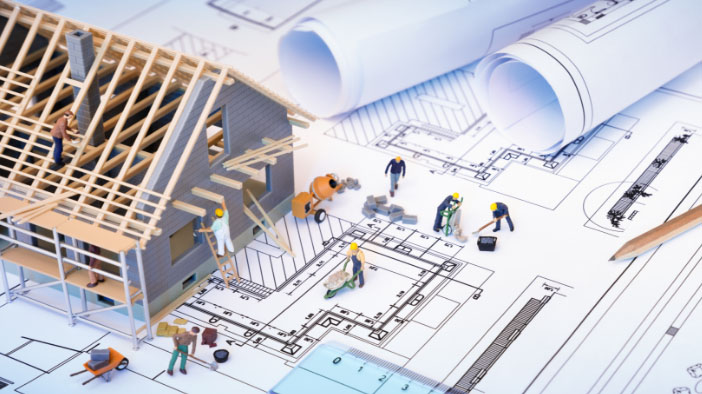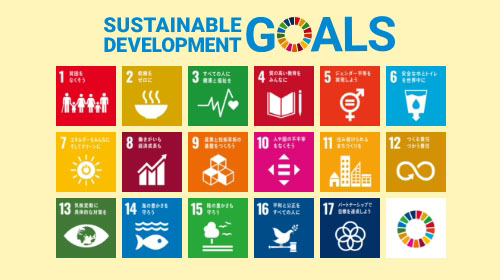リフォーム補助金は活用しないと損!知っておきたい3つの重要ポイント
ご自宅のリフォーム費用を抑えるには、国や地方自治体が実施する補助金制度の活用が有効です。制度を上手に利用すれば、高額な工事費用を大幅に軽減できる可能性があります。しかし、仕組みをよく理解しないままでは、申請の好機を逃しかねません。リフォーム補助金を賢く利用するために知っておくべき3つのポイントを解説します。
【POINT1】補助金は誰でももらえる?対象となるリフォームと申請の条件
補助金の対象となるリフォーム工事には、様々な種類があります。ただし、住宅の機能向上を伴わない、単なる壁紙の張り替えといった内装工事は対象外です。
補助金の対象となる代表的なリフォーム工事を紹介しましょう。
<補助金の対象となる主なリフォーム工事>
| リフォームの種類 |
工事例 |
主な補助金制度 |
| 省エネリフォーム |
・窓や玄関ドア、ガラスの交換(内窓設置、外窓交換)
・外壁、床、屋根への断熱材設置
・高効率給湯器(エコキュート、エネファーム等)の設置
・高断熱浴槽や節水型トイレの設置 |
・子育てグリーン住宅支援事業
・先進的窓リノベ2025事業 |
| 耐震リフォーム |
・基礎や柱、梁の補強、耐力壁の新設
・瓦屋根から軽量な屋根材への変更 |
・長期優良住宅化リフォーム推進事業
・地方自治体の耐震改修助成制度 |
| バリアフリーリフォーム |
・手すりの設置、段差の解消 |
・介護保険の住宅改修 |
補助金を受け取るための主な条件
補助金を受け取るための条件は、制度ごとに異なります。一般的には、以下のような要件を満たす必要があります。
<リフォームの補助金を受け取るための条件>
・補助対象となる住宅の所有者本人である。
・制度で定められた対象工事の要件を満たす。
・定められた期間内に工事に着手し、完了させる。
・子育て世帯といった世帯要件が設定されている場合は、条件に合致する。
・補助金制度に登録された事業者による施工である。
|
【POINT2】補助金はいつもらえる?申請のタイミングと補助金受領までの流れ
リフォーム補助金は、原則として工事が完了し、費用の支払いを終えた後に受け取る「後払い」です。申請手続きは施工業者が代行する場合が多く、申請の時期は制度ごとに工事着手前や完了後などと定められています。申請後には審査があり、受領までには数週間から数カ月を要します。また、ほとんどの制度には年間予算があり、上限に達し次第終了するため、工事計画と資金計画の連携が重要です。
【POINT3】国と自治体の補助金は併用できる?
ひとつの工事に対して条件に合う補助金が複数ある場合、国の制度と地方自治体が独自に行う制度は、基本的に併用できます。注意点として、自治体が窓口でも、補助金の財源が国費の場合は、他の国の制度とは併用できません。リフォームを依頼する施工事業者に相談し、利用できる制度を漏れなく活用しましょう。
【2026年度版】国が支援するリフォーム補助金活用術
リフォームを計画する際に、大きな助けとなるのが国の補助金制度です。2026年度も、住宅の性能向上や子育て世帯への支援を目的とした、多様な事業が実施される予定です。上手に活用すれば、リフォーム費用の負担を軽減できるでしょう。
国が支援する補助金はどんな種類がある?
国の補助金制度は、省エネ改修を目的とした「住宅省エネ2025キャンペーン」をはじめ、住宅の長寿命化やバリアフリー化など、多様なニーズに対応する支援策が用意されています。ご自身の計画に合った制度を見つけるために、まずは全体像を把握しましょう。
<リフォームに関する国の補助金一覧>
| 分類 |
事業名 |
概要 |
| 住宅省エネキャンペーン |
みらいエコ住宅2026事業 |
住宅の省エネ改修(断熱工事やエコ住宅設備の設置)を支援する制度です。省エネ改修と併せて行うことで、子育て対応改修、バリアフリー改修、防災性向上改修なども補助の対象となります。 |
| 先進的窓リノベ2026事業 |
断熱性の高い窓への交換など、開口部の断熱性能向上のための工事に特化しています。 |
| 給湯省エネ2026事業 |
高効率給湯器の導入を支援し、家庭のエネルギー消費量を削減する目的です。 |
| その他の主要な補助金 |
住宅・建築物省エネ改修推進事業 |
既存住宅の省エネ化だけでなく、長寿命化や子育て対応、防犯対策など、地域の課題解決に役立つ改修を総合的に支援する枠組みです。 |
| 介護保険における住宅改修 |
要支援・要介護認定を受けた方が対象。手すりの設置や段差解消など、バリアフリー改修費用の一部が支給される制度です。 |
リフォームで賢く節税!税の特例措置とは?
住宅のリフォームでは、条件を満たすと所得税や固定資産税の優遇措置を受けられます。納税者にとって有利な制度が用意されており、特に所得税の控除は高い節税効果を期待できる仕組みです。
所得税の優遇措置 どちらを選ぶべきか
リフォームで利用できる所得税の優遇措置には、大きく分けて2種類あります。両方の制度を併用はできず、自身の状況に合わせて有利な方を選択する必要があります。
<所得税の優遇措置比較の概要>
| 制度の種類 |
住宅ローン減税(リフォーム) |
リフォーム促進税制(目的別の税額控除) |
| 制度の概要 |
10年以上のローンを組んでリフォームした場合、年末ローン残高の0.7%を10年間にわたり所得税額から控除します(借入限度額2,000万円)。 |
ローン利用の有無にかかわらず、特定の改修工事を行った場合、標準的な工事費用の10%などを単年で所得税額から控除します。 |
| 対象となる主な改修 |
・増改築、大規模な修繕
・耐震、バリアフリー、省エネ改修など |
・耐震改修
・バリアフリー改修・省エネ改修
・三世代同居対応改修など |
| 選択のポイント |
・借入額が大きく、長期間にわたって控除を受けたい場合に有利です。
・幅広いリフォームが対象になります。 |
・自己資金でリフォームする場合や、ローン期間が10年未満の場合に選択します。
・特定の改修に特化した場合に有利な場合があります。 |
固定資産税の減額措置
特定の性能向上リフォームを実施すると、工事完了の翌年度分に限り、家屋の固定資産税が減額されます。
<固定資産税の減額措置の概要>
| 改修の種類 |
減額内容 |
主な要件 |
| 耐震改修 |
固定資産税額の1/2を減額 |
1982年1月1日以前に建築された住宅である必要があります。 |
| バリアフリー改修 |
固定資産税額の1/3を減額 |
65歳以上の方などが居住している必要があります。 |
| 省エネ改修 |
固定資産税額の1/3を減額 |
窓の断熱改修などが必須工事となります。 |
【国のリフォーム補助金.1】住宅省エネキャンペーンを徹底解説
住宅の省エネ化を支援する4つの補助事業をまとめた「住宅省エネキャンペーン」。断熱改修や高効率給湯器の導入を検討しているなら、ぜひ活用したい制度です。
1つの工事契約で複数の補助金を申請できますが、同じ設備に対して重複した申請はできません。例えば、リビングの窓は先進的窓リノベで申請し、浴室の断熱工事をみらいエコで申請するのは可能です。しかし、高効率給湯器を給湯省エネで申請した場合、みらいエコの対象からは外れます。補助金の申請は登録事業者が行うため、まずは信頼できるリフォーム会社へ相談しましょう。
戸建て住宅で特に利用しやすい3つの事業を紹介します。
みらいエコ住宅2026事業は幅広い工事が対象
高い省エネ性能を持つ住宅の新築やリフォームを支援する制度です。リフォームの場合、名称とは異なり子育て世帯や若者夫婦世帯以外も対象となる点が大きな特徴です。
<みらいエコ住宅2026事業(リフォーム)の概要>
| 項目 |
内容 |
| 補助対象者 |
全世帯(子育て世帯や若者夫婦世帯以外も対象となります) |
| 対象となる工事 |
【必須工事】開口部、外壁、屋根・天井又は床の断熱改修、エコ住宅設備の設置の組合せ
【任意工事】必須工事とあわせて実施する場合に補助対象となります。(子育て対応改修、バリアフリー改修、防災性向上改修など) |
| 補助上限額 |
最大 100万/戸
※「改修前の省エネ性能」と「改修後の省エネ性能」の組み合わせにより、上限額が段階的に設定されます(例:100万円、80万円、50万円、40万円など)。 |
| 申請期間 |
2025年11月28日(着工・契約)~(予算上限に達し次第、早期に終了する可能性があります) |
| 申請方法 |
あらかじめ登録された施工業者が申請手続きを代行します。 |
「先進的窓リノベ2025事業」は光熱費削減に直結
既存住宅の省エネ化を促進し、エネルギー費用負担の軽減と快適な室内環境の実現を目指す補助金制度が「先進的窓リノベ2026事業」です。
住宅の熱の出入りが最も大きい場所は「窓」といわれます。窓の断熱性を高める改修は、冷暖房効率を大幅に改善するため、光熱費の削減に直結する非常に費用対効果の高いリフォームといえるでしょう。
<先進的窓リノベ2026事業の概要>
| 項目 |
内容 |
| 対象となる工事 |
高断熱窓(熱貫流率Uw1.9以下等、建材トップランナー制度2030年目標水準値を超えるもの、その他要件を満たすもの等) |
| 補助上限額 |
100万円/戸
(補助額が非常に大きい点が大きな魅力です) |
| 申請期間 |
予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで) |
| 申請の注意点 |
補助金の申請は、あらかじめ登録された施工業者が代行します。
まずは相談できるリフォーム会社を探すことから始めましょう。 |
「給湯省エネ2026事業」は光熱費を大きく削減
家庭におけるエネルギー消費の約3割を占める給湯分野の省エネ化を推進する制度が「給湯省エネ2026事業」です。高効率給湯器へ交換すると、日々の光熱費を効果的に抑えられるでしょう。
<給湯省エネ2026事業の概要>
| 項目 |
内容 |
| 対象となる工事 |
・ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
・ハイブリッド給湯機
・家庭用燃料電池 |
補助金額
【基本額】 |
(戸建て住宅はいずれか2台まで)
主な補助金額
・ヒートポンプ給湯機:10万円/台・ハイブリッド給湯機:12万円/台
・家庭用燃料電池:17万円/台 |
補助金額
【撤去加算】 |
・蓄熱暖房機撤去:4万円/台(2台まで)
・電気温水器撤去:2万円/台(高効率給湯器導入により補助を受ける台数まで) |
| 申請期間 |
予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで) |
| 申請方法 |
あらかじめ登録された施工業者が申請手続きを代行します。 |

【国のリフォーム補助金.2】既存住宅における断熱リフォーム支援事業を徹底解説
既存住宅の断熱性能向上を支援する補助金制度です。公益財団法人北海道環境財団が運営していますが、全国の住宅が対象となります。
家全体の断熱性を高めるか、生活の中心である居間に絞って改修するか、目的に応じてプランを選べる点が大きな特徴です。
<既存住宅における断熱リフォーム支援事業の概要>
| 項目 |
内容 |
| 選べる改修プラン |
以下のいずれかを選択します。
【トータル断熱】
高性能な断熱材や窓を使い、家全体を断熱改修するプラン。玄関ドアも対象です。
【居間だけ断熱】
生活の中心となる居間に絞り、高性能な窓で断熱改修するプラン。 |
| 補助金額 |
補助率:対象経費の1/3以内
【トータル断熱の補助上限額】
・戸建て住宅:120万円/戸(玄関ドア改修費5万円分を含む) |
追加設備の補助額
(トータル断熱で選択) |
・家庭用蓄電システム:20万円
・家庭用蓄熱設備:20万円
・熱交換型換気設備:5万円 |
申請期間
(予定) |
2026年1月以降 |
【国のリフォーム補助金.3】既築住宅のZEH化改修促進支援を解説
既存の戸建て住宅のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)化を支援する補助金制度です。2026年度の実施が予定されています。
<既築住宅のZEH化改修促進支援の概要>
| 項目 |
内容 |
| 事業の目的 |
既存住宅において、ZEHを超える高い水準の省エネ性能を達成する改修工事の実証を支援します。 |
| 補助金額 |
・改修に要する費用の3分の1相当を定額補助(上限250万円/戸)
・既存住宅の省エネ診断に対して定率補助(1/3) |
| 申請期間 |
未定 |
【国のリフォーム補助金.4】介護保険の住宅改修について徹底解説
要支援・要介護認定を受けた方が、自宅で安全に暮らし続けるための小規模なリフォーム費用を支援する制度が「介護保険の住宅改修」です。被介護者の自立を助け、介護者の負担を軽くする目的があります。
他の補助金と異なり、工事の前に市区町村への申請が必須となるなど、手続きの手順が非常に重要です。
<介護保険の住宅改修の概要>
| 項目 |
内容 |
| 対象者 |
要支援1~2または要介護1~5の認定を受けている方 |
| 対象となる主な工事 |
・手すりの取付け(玄関、廊下、階段、浴室、トイレなど)
・段差の解消(敷居の撤去、スロープ設置など)
・床材の変更(滑りにくい床材への変更など)
・扉の取替え(開き戸から引き戸への変更など)
・便器の取替え(和式から洋式への変更など)
・上記工事に付帯して必要となる改修 |
| 支給上限額 |
20万円まで
(費用のうち、所得に応じて1割から3割が自己負担となります) |
| 申請の窓口 |
各市区町村の介護保険担当窓口 |
| 申請期間 |
通年で申請できます。 |
| 補足 |
この制度を利用する際は、まず担当のケアマネジャーへの相談が不可欠です。必要な改修内容を相談し、理由書を作成してもらった上で、必ず工事着工前に市区町村へ申請します。手順を間違えると支給対象外となるため、計画的に進めましょう。 |
【意外と見落としがち】お住まいの自治体にもあるリフォーム補助金
リフォームで利用できる補助金は、国の制度だけではありません。各地方自治体も、地域の実情に合わせた独自の補助金や助成制度を設けています。
国の制度と併用できる場合もあり、組み合わせることで大きな経済的支援を受けられるかもしれません。まずは、お住まいの地域にどのような制度があるか調べてみましょう。
地方自治体の補助金を探す方法
ご自身の居住エリアのリフォーム補助金情報を調べるには、以下の方法が考えられます。補助金制度は年度ごとに内容や要件が変わるため、必ず最新の情報を確認してください。
【事例紹介】2025年に実施していた地方自治体のリフォーム補助金
ここでは、地方自治体が実施しているリフォーム補助金の一例を紹介します。既に2025年度の受付を終了している制度も含まれますが、お住まいの地域でどのような支援策が期待できるかの参考にしてください。なお、補助金額は2025年度のものです。
<主な地方自治体のリフォームの補助金制度>
| 自治体名 |
制度名 |
主な対象工事 |
補助金額
(上限など) |
備考 |
| 東京都 |
既存住宅省エネ診断・設計等支援事業 |
省エネ性能診断、断熱設計など |
・省エネ診断 上限21万円
・省エネ設計 上限18~36万円 |
都内の既存住宅が対象
・2025年度分の申請は2026年2月16日まで |
| 愛知県名古屋市 |
木造住宅耐震改修助成 |
木造住宅の耐震改修 |
工事費の4/5
(上限115万円) |
・昭和56年5月31日以前着工の木造住宅が対象
・2025年度分の申請は2026年1月末まで |
| 神奈川県 |
既存住宅省エネ改修事業費補助金 |
指定製品を用いた省エネ改修 |
対象経費の1/3または20万円のいずれか低い額 |
2025年度は受付終了
耐震性を確保した住宅が対象 |
| 大阪府大阪市 |
住宅省エネ改修促進事業 |
省エネ対策工事、省エネ設備の設置 |
【ZEHレベル】
補助率4/5(上限70万円)
【省エネ基準レベル】
補助率2/5(上限30万円) |
・昭和56年6月1日以降着工の建物が対象
・2025年度分の申請は2026年1月末まで |
| 兵庫県神戸市 |
住宅改修助成事業 |
バリアフリー改修 |
上限100万円 |
一定の高齢者または障害者で所得要件あり |
| 千葉県千葉市 |
木造住宅耐震改修補助制度 |
耐震改修 |
補助率4/5
(上限115万円) |
2025年度は受付終了
耐震診断で「倒壊の可能性あり」と判断された住宅が対象 |
リフォーム補助金の不安、
専門家と解消しませんか?
リフォームで利用できる補助金や税の優遇制度は、国や自治体から数多く提供されており、賢く活用すればリフォーム費用を大幅に抑えられます。
しかし、制度の要件は複雑で、申請手続きにも専門的な知識が必要。
「どの制度が自分のリフォームに使えるのか分からない」
「申請のタイミングを逃してしまいそう」
…といった不安を感じる方もいらっしゃるのでは?

成功の鍵は「信頼できるパートナー選び」
こうした複雑な制度を最大限に活用し、リフォームを成功に導く鍵は、補助金制度に精通した信頼できる専門家をパートナーに選ぶ作業です。
経験豊富な事業者であれば、国や自治体の最新の補助金情報を常に把握しており、お客様のリフォーム計画に最適な制度の組み合わせを提案できます。
ご自身で複雑な制度を調べる手間が省けるだけでなく、「知らなかった」ために利用できるはずの支援を逃すといった事態も防げるでしょう。

補助金活用のプロ「アエラのリフォー夢」にお任せください
私たちアエラホームの「アエラのリフォー夢」では、これまで数多くの補助金活用リフォームを手掛けてきた実績があります。
豊富な実績と最新情報で最適なプランをご提案
国の「住宅省エネキャンペーン」はもちろん、お住まいの自治体が独自に設ける助成制度まで、最新の情報を常に把握しています。
経験豊富な専門スタッフが、お客様一人ひとりのご計画やご予算を丁寧にお伺いし、利用可能な補助金を組み合わせた最適なリフォームプランと資金計画をご提案します。
なお、お問い合わせからお見積りまで、一切費用はかかりません。

面倒な申請手続きもフルサポート
複雑で面倒な申請手続きも、私たちが責任を持って代行サポートいたしますので、ご安心ください。「まずは話だけ聞いてみたい」という方も大歓迎です。
お客様の理想の住まいづくりを、資金計画の面から力強くサポートします。詳しい情報やご相談は、ぜひ公式サイトからお問い合わせください。
【確実に受け取るために】補助金申請のステップと成功の秘訣
リフォームの補助金を受け取るには、申請から受給までに複数のステップを踏む必要があります。複雑な手続きや専門的な知識が求められるため、戸惑う方も多いでしょう。補助金を確実に受け取るための重要なポイントと、具体的な申請から受給までの流れを解説します。
申請から補助金を受け取るまでの流れ
リフォーム補助金の申請から受給までの一般的な流れは、以下の通りです。特に、工事着工前に申請と交付決定が必要な点を覚えておきましょう。
<1>事業者選びとプラン相談
補助金制度に詳しいリフォーム会社を選び、利用したい制度の対象となる工事内容や製品について相談し、計画を固めます。
<2>事前申請と交付決定通知
リフォーム会社を通じて、必要な書類を揃えて補助金の交付申請を行います。審査を経て、交付が決定されると通知が届きます。
<3>リフォーム工事の着工・完了
交付決定通知を受けた後、リフォーム工事を開始します。
<4>完了実績報告書の提出
工事が完了したら、期限内に完了実績報告書を提出します。
<5>補助金額の確定と受給
提出された報告書を基に補助金額が最終的に確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
補助金申請は専門家への依頼が成功の鍵
リフォーム補助金の申請は、施工事業者(住宅メーカーやリフォーム会社)へ任せるのが最も確実な方法です。多くの制度では、登録事業者でなければ申請手続きができません。
補助金制度に精通した事業者へ依頼すると、書類作成や提出の手間が省けるだけでなく、複数の制度を上手に併用するための専門的な助言も期待できます。結果として、リフォームの費用対効果を最大限に高められるのです。
【FPからアドバイス】補助金活用の成否は信頼できる事業者選びで決まる
リフォームで利用できる支援制度は、国の補助金から地方自治体の助成、税の特例措置まで多岐にわたります。それぞれの制度は目的や要件が異なり、申請手続きも複雑な場合が少なくありません。
こうした多様な制度の中から最適な組み合わせを見つけ出し、最大限に活用するための最も確実な方法は、補助金制度に精通した経験豊富な住宅メーカーやリフォーム会社をパートナーに選ぶ作業です。
信頼できる事業者へ相談すれば、計画に合った補助金の提案から複雑な申請手続きの代行までを任せられ、不備なくスムーズな受給につながります。賢い事業者選びこそが、リフォームを成功に導く最初の、そして最も重要な一歩といえるでしょう。